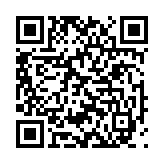スポンサーリンク
タマネギの播種は地味な作業です。
2009年09月26日
むさしの農業ふれあい村では会員さんや農業塾の塾生に向けて
毎月「むさしの農業ふれあい村だより」というもの発行しています。
今月は、昨年の12月からふれあい村を取材している主婦の友社のO氏が
これまで撮った写真から厳選したものを提供してくれました!
※来年の2月には出版本として多くの写真が掲載されるようですよ!!
この「むさしの農業ふれあい村だより」は公式サイトからバックナンバーも合わせて
見る事ができます。⇒コチラ
本日の作業は
①タマネギの播種
②カブ・白菜・ダイコンの間引き
③カカシ作り
作業前のミニ講義ではタマネギ担当のY氏が図解を交えて
分かりやすいレクチャーをしてくれました。
最初に質問がありました。
「タマネギの食べる部分は実なのか?根なのか??茎なのか???それとも・・・」


正解は「葉っぱ=葉鞘(ようしょう)」です。
タマネギをむくと幾重にもなっているのが葉なんですって!?
そしてタマネギがあの形に膨らむためにリンが必要との事。
以前にタマネギの苗床を作りました。
ここに播種(種まき)をします。

この溝に2cm間隔で種を一粒づつ蒔きます。
はい、とっても地味な作業です。
作業風景をご覧下さい。


・・・
・・・
こんな格好になってしまいました(笑)

一方、別の作業班は間引きの作業を


ん?バケツ一杯に間引いていますね。

ここで私はゴーヤの収穫へ。
ゴーヤも今年最後の収穫、自宅に帰って切ってみると種が
赤くなっていました。
(写真はありません)
タマネギの苗床へ戻りましょう。
種を蒔いた上から土を振るい、その上でパオパオ(マルチとは違います)で
覆いました。
パオパオの上からたっぷりの水をあたえ作業終了です。
(タマネギは乾燥を嫌うためパオパオで保湿効果を高めているのかな??)



そうそう、タマネギにも多くの種類があり、今回は
■ソニック
■ターボ
■泉州中高黄
■泉州黄大玉葱
の4種類を蒔きました。

私の担当であるキャベツも小さな球が出来ていました。
そろそろ講義の為に調べないとあかんなぁ。


毎月「むさしの農業ふれあい村だより」というもの発行しています。
今月は、昨年の12月からふれあい村を取材している主婦の友社のO氏が
これまで撮った写真から厳選したものを提供してくれました!
※来年の2月には出版本として多くの写真が掲載されるようですよ!!
この「むさしの農業ふれあい村だより」は公式サイトからバックナンバーも合わせて
見る事ができます。⇒コチラ
本日の作業は
①タマネギの播種
②カブ・白菜・ダイコンの間引き
③カカシ作り
作業前のミニ講義ではタマネギ担当のY氏が図解を交えて
分かりやすいレクチャーをしてくれました。
最初に質問がありました。
「タマネギの食べる部分は実なのか?根なのか??茎なのか???それとも・・・」
正解は「葉っぱ=葉鞘(ようしょう)」です。
タマネギをむくと幾重にもなっているのが葉なんですって!?
そしてタマネギがあの形に膨らむためにリンが必要との事。
以前にタマネギの苗床を作りました。
ここに播種(種まき)をします。
この溝に2cm間隔で種を一粒づつ蒔きます。
はい、とっても地味な作業です。
作業風景をご覧下さい。
・・・
・・・
こんな格好になってしまいました(笑)
一方、別の作業班は間引きの作業を
ん?バケツ一杯に間引いていますね。
ここで私はゴーヤの収穫へ。
ゴーヤも今年最後の収穫、自宅に帰って切ってみると種が
赤くなっていました。
(写真はありません)
タマネギの苗床へ戻りましょう。
種を蒔いた上から土を振るい、その上でパオパオ(マルチとは違います)で
覆いました。
パオパオの上からたっぷりの水をあたえ作業終了です。
(タマネギは乾燥を嫌うためパオパオで保湿効果を高めているのかな??)
そうそう、タマネギにも多くの種類があり、今回は
■ソニック
■ターボ
■泉州中高黄
■泉州黄大玉葱
の4種類を蒔きました。
私の担当であるキャベツも小さな球が出来ていました。
そろそろ講義の為に調べないとあかんなぁ。
無農薬野菜を作るのは並大抵の事ではありません
2009年09月22日
9月19日の作業

ミニ講義は農薬について
※「むさしの農業ふれあい村」が作っている作物は無農薬ではなく
減農薬野菜です。
安全な国産野菜を食べたい、と家庭菜園での野菜作りがちょっとしたブームに
なっているようですが、完全無農薬で野菜を作ることは難しいのが現状です。
下手をするとまともな収穫が出来ないと言う自体も!!
農薬を上手に使って一定の収穫量は確保したいものです。
とは言え、ふれあい村では無農薬での野菜で作りへの挑戦は行っていくようですけどね。



農薬はその用途によって
殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌剤、除草剤、殺鼠(さっそ)剤、植物成長調整剤、
誘引剤、展着剤(てんちゃくざい)、天敵、微生物剤に分類されます。
※ 農薬情報については
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
のサイトで得ることが出来ます。
☆写真で綴る作業風景☆
葉っぱが食われていました。


<サツマイモのつる返し>
畝も見えないほど畑一面をサツマイモの葉が覆っていた。
サツマイモのツルは自由奔放に伸び放題、このツルの節々には根があり
これを土から剥がさないと栄養がイモに行き届かない。
その為、つる返し(つる起こし)をする必要がある。







ミニ講義は農薬について
※「むさしの農業ふれあい村」が作っている作物は無農薬ではなく
減農薬野菜です。
安全な国産野菜を食べたい、と家庭菜園での野菜作りがちょっとしたブームに
なっているようですが、完全無農薬で野菜を作ることは難しいのが現状です。
下手をするとまともな収穫が出来ないと言う自体も!!
農薬を上手に使って一定の収穫量は確保したいものです。
とは言え、ふれあい村では無農薬での野菜で作りへの挑戦は行っていくようですけどね。
農薬はその用途によって
殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌剤、除草剤、殺鼠(さっそ)剤、植物成長調整剤、
誘引剤、展着剤(てんちゃくざい)、天敵、微生物剤に分類されます。
※ 農薬情報については
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
のサイトで得ることが出来ます。
☆写真で綴る作業風景☆
葉っぱが食われていました。
<サツマイモのつる返し>
畝も見えないほど畑一面をサツマイモの葉が覆っていた。
サツマイモのツルは自由奔放に伸び放題、このツルの節々には根があり
これを土から剥がさないと栄養がイモに行き届かない。
その為、つる返し(つる起こし)をする必要がある。
苗床作りと公園整備
2009年09月12日
本日の作業内容です。

ふれあい村では先日より作業前にミニ講義を実施する事になりました。
と同時に野菜ごとに作業担当者を決めて、責任を持って収穫まで育てる事に。
私の担当は’キャベツ’になりました。
今日は’コカブ’の担当者である草取り名人のOさんが初講義を行いました。
コカブの原産地や播種(種まき)の時期、土の深さ、一つの穴に何個蒔くかなどを
レクチャーしてくれました。
立派な講義に他の野菜の担当者も「これはしっかり勉強せなアカンなぁ」と
心の中で思ったはず!?


私の今日の担当作業は「タマネギの苗床」作りでした。
農家によると苗床を作らずに栽培を行う事もあるようですが、ふれあい村では
教科書通り、苗床で育ててから植え付けをします。
苗床の土作りには1㎡当たり
●堆肥 ・・・2kg
●化成肥料 ・・・200g
●有機リン(だったかな?)・・・60g
を蒔いて耕します。
何もないこの場所に

耕運機をかけ、


ちなみにこの耕運機は「陽菜」です!

と、ここで私はゴーヤの収穫に借り出され(笑)、戻ってくると
苗床は最終段階に入っていました。


15cmおきに溝を作っていました。
種まきは本日行いませんが、種がどのくらい必要かを調べるためです。


6~7㎡の苗床の完成です!!
向こうでは何をしているのかな?

コカブを植えた畑に寒冷紗(かんれいしゃ)??


畑での作業を終えた後は公園の雑草取りをしました。
むさしの農業ふれあい村が活動している農業ふれあい公園は
農業が出来る畑と果樹や花木が植えられた公園がある都市型公園なんですよ!


天気予報どおり作業の終盤から雨がポツポツ落ちてきました。
伸び放題だった雑草を山ができるほど抜きスッキリしました!


田んぼも気付けば黄金色、秋は近づいていたんですね。


【今日の一枚:ふれあい村のシンボル”長屋門”】

ふれあい村では先日より作業前にミニ講義を実施する事になりました。
と同時に野菜ごとに作業担当者を決めて、責任を持って収穫まで育てる事に。
私の担当は’キャベツ’になりました。
今日は’コカブ’の担当者である草取り名人のOさんが初講義を行いました。
コカブの原産地や播種(種まき)の時期、土の深さ、一つの穴に何個蒔くかなどを
レクチャーしてくれました。
立派な講義に他の野菜の担当者も「これはしっかり勉強せなアカンなぁ」と
心の中で思ったはず!?
私の今日の担当作業は「タマネギの苗床」作りでした。
農家によると苗床を作らずに栽培を行う事もあるようですが、ふれあい村では
教科書通り、苗床で育ててから植え付けをします。
苗床の土作りには1㎡当たり
●堆肥 ・・・2kg
●化成肥料 ・・・200g
●有機リン(だったかな?)・・・60g
を蒔いて耕します。
何もないこの場所に
耕運機をかけ、
ちなみにこの耕運機は「陽菜」です!
と、ここで私はゴーヤの収穫に借り出され(笑)、戻ってくると
苗床は最終段階に入っていました。
15cmおきに溝を作っていました。
種まきは本日行いませんが、種がどのくらい必要かを調べるためです。
6~7㎡の苗床の完成です!!
向こうでは何をしているのかな?
コカブを植えた畑に寒冷紗(かんれいしゃ)??
畑での作業を終えた後は公園の雑草取りをしました。
むさしの農業ふれあい村が活動している農業ふれあい公園は
農業が出来る畑と果樹や花木が植えられた公園がある都市型公園なんですよ!
天気予報どおり作業の終盤から雨がポツポツ落ちてきました。
伸び放題だった雑草を山ができるほど抜きスッキリしました!
田んぼも気付けば黄金色、秋は近づいていたんですね。
【今日の一枚:ふれあい村のシンボル”長屋門”】
わけぎを植えて、ジャガイモを埋める
2009年09月06日
これ、何のミニ球根だか分かりますか?

’わけぎ’なんです。
わけぎってネギとタマネギの雑種なんですね。(Wikipedia参照:ワケギ)
全ての球根が育つとは限らないので一つの箇所に2つのわけぎを60cm間隔くらいで
植えていきました。


若干、曲がってしまったような気がするけど
無事に植え付けを終えましたよ!

新しいジャガイモも土の中に・・・
埋める前に芽を外した表面をカットしました。

この切り込みはジャガイモに危機感を与えるため。
こうする事でジャガイモの生命力が増すようです、種の保存ってわけかな。
更に灰をまぶしてから埋めました。


今年は日照不足のおかげで野菜の値段が上がっていますね。
ふれあい村でも夏野菜の収穫が心配されましたが、毎回、会員へ配布する分は
しっかり確保できました。
やはり相手が自然ということで思い通りにはなかなかいかない。
だからこそ野菜作りの面白みがあり、人間も自然の一部だという事が
分かるような気がします。

ジャガイモの種類は何だったかなぁ??
’わけぎ’なんです。
わけぎってネギとタマネギの雑種なんですね。(Wikipedia参照:ワケギ)
全ての球根が育つとは限らないので一つの箇所に2つのわけぎを60cm間隔くらいで
植えていきました。
若干、曲がってしまったような気がするけど
無事に植え付けを終えましたよ!
新しいジャガイモも土の中に・・・
埋める前に芽を外した表面をカットしました。
この切り込みはジャガイモに危機感を与えるため。
こうする事でジャガイモの生命力が増すようです、種の保存ってわけかな。
更に灰をまぶしてから埋めました。
今年は日照不足のおかげで野菜の値段が上がっていますね。
ふれあい村でも夏野菜の収穫が心配されましたが、毎回、会員へ配布する分は
しっかり確保できました。
やはり相手が自然ということで思い通りにはなかなかいかない。
だからこそ野菜作りの面白みがあり、人間も自然の一部だという事が
分かるような気がします。
ジャガイモの種類は何だったかなぁ??
寒冷紗作業の一部始終
2009年09月05日
こんばんは、カズです。
3日涼しい日が続きましたが、今日は残暑が厳しい一日でした。
でも、曇り空よりはやっぱり晴天の方が気持ちいいです。
むさしの農業ふれあい村は3週間ぶりです。
村の入り口でMさんに会うと、
「明日は雨だなぁ。」
と言われてしまいました(汗)
サトイモがこんなに大きく育っていました!
小さな子供が持ったら傘に出来そうなほどです。


今日の主な作業は寒冷紗(かんれいしゃ)の設置とワケギの植付けでした。
マルチを張った畝(うね)の両サイドに溝切りをします。


写真のように棒を突き刺します。


二人がかりで寒冷紗を張り、溝切りの時に寄せた土を寒冷紗の裾に被せて
固定します。
※間引きなど寒冷紗を捲らなければならないので片方だけをしっかりと固定し、
もう片方は軽く土を被せました。(今回は北側を固定)


さらに写真のように棒を深く刺して強度をアップ!

キレイに寒冷紗が設置できました!


寒冷紗を設置する目的は色々とあるけど、今回の一番の目的は防虫です。
特にダイコンやカブは植えてから最初の一ヶ月が勝負だそうです。(村長談)
この段階で葉を食われてしまうと実が育たず収穫ができません。
(寒冷紗の設置前には消毒を行っています)
【今日の一枚:Yさんが収穫した珍しいナス】

3日涼しい日が続きましたが、今日は残暑が厳しい一日でした。
でも、曇り空よりはやっぱり晴天の方が気持ちいいです。
むさしの農業ふれあい村は3週間ぶりです。
村の入り口でMさんに会うと、
「明日は雨だなぁ。」
と言われてしまいました(汗)
サトイモがこんなに大きく育っていました!
小さな子供が持ったら傘に出来そうなほどです。
今日の主な作業は寒冷紗(かんれいしゃ)の設置とワケギの植付けでした。
マルチを張った畝(うね)の両サイドに溝切りをします。
写真のように棒を突き刺します。
二人がかりで寒冷紗を張り、溝切りの時に寄せた土を寒冷紗の裾に被せて
固定します。
※間引きなど寒冷紗を捲らなければならないので片方だけをしっかりと固定し、
もう片方は軽く土を被せました。(今回は北側を固定)
さらに写真のように棒を深く刺して強度をアップ!
キレイに寒冷紗が設置できました!
寒冷紗を設置する目的は色々とあるけど、今回の一番の目的は防虫です。
特にダイコンやカブは植えてから最初の一ヶ月が勝負だそうです。(村長談)
この段階で葉を食われてしまうと実が育たず収穫ができません。
(寒冷紗の設置前には消毒を行っています)
【今日の一枚:Yさんが収穫した珍しいナス】
タグ :むさしの農業ふれあい村寒冷紗